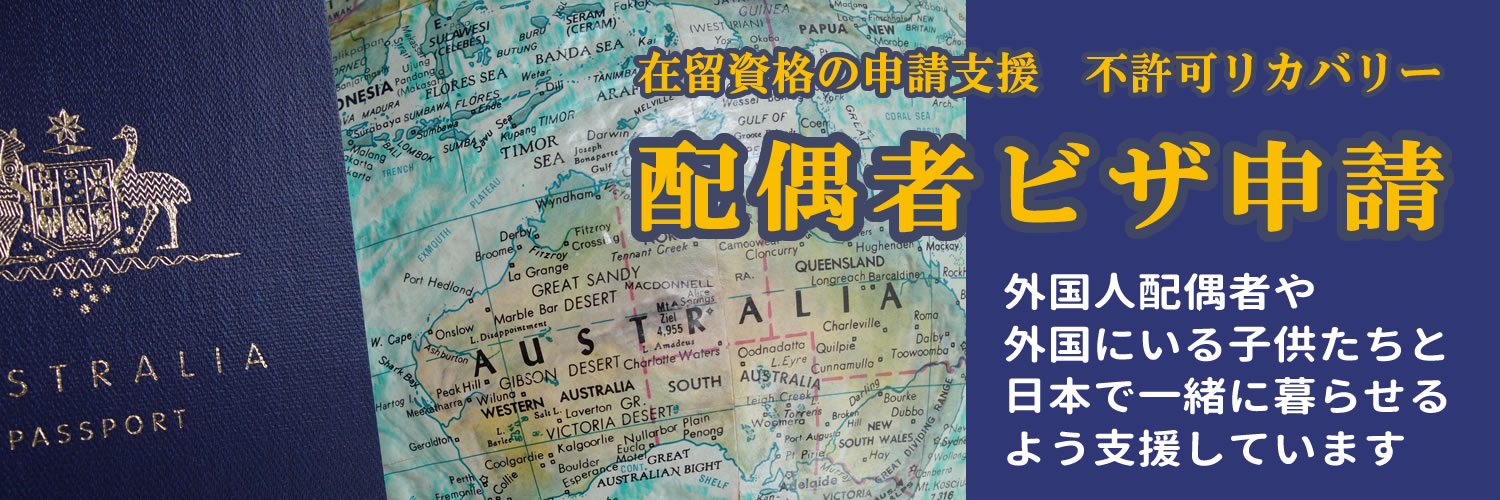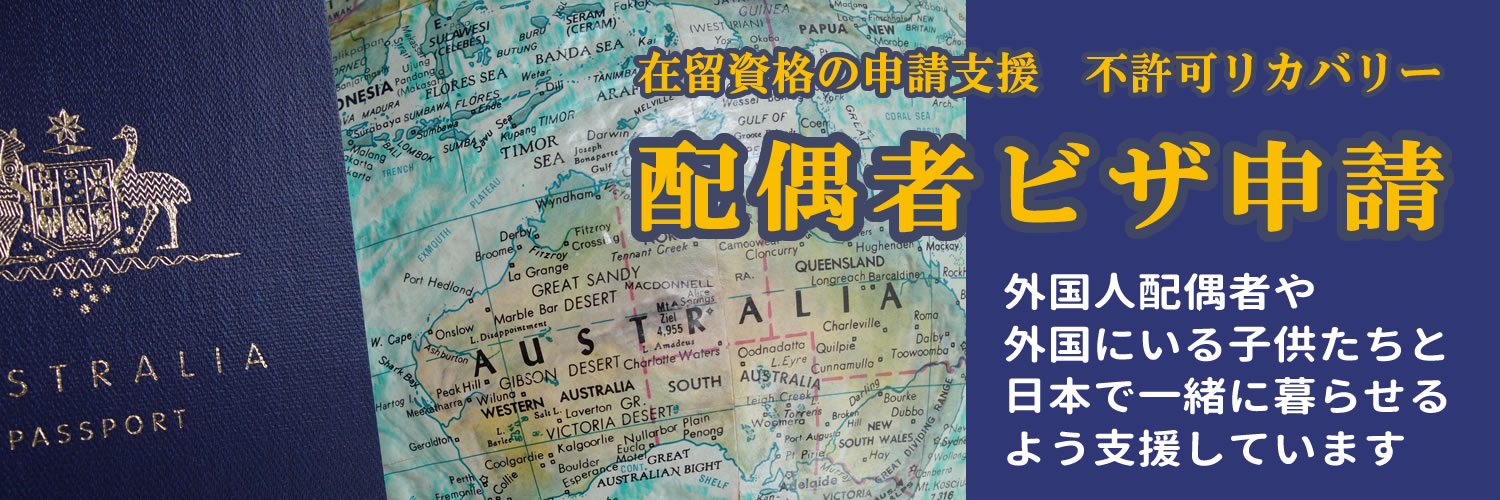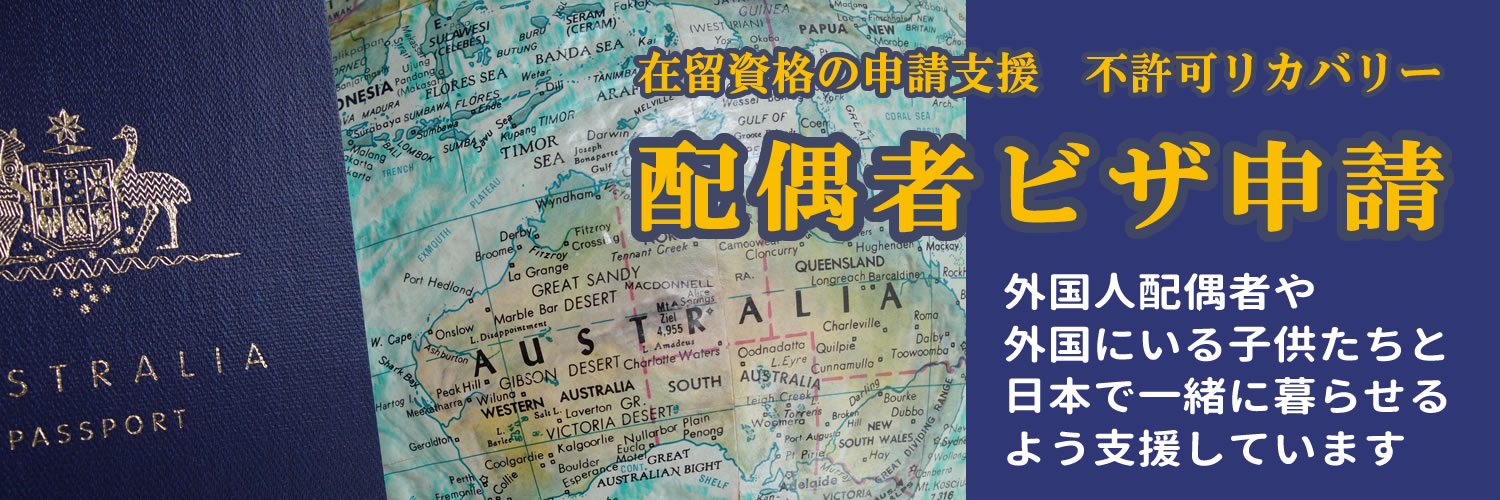
シモン行政書士事務所のホームページへ
- ※本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。
政府は、今後の厳格化について、2026年1月に基本的な方向性を取りまとめるとしています。「在留資格の再検討」「帰化の厳格化」「他省庁のデータと審査の連動」「人口戦略」「永住許可や帰化の取消し」「不法外国人対策」「手数料の見直し」などが主なテーマとなっています。今後は申請の正当性を説明できないと許可の取得が難しくなります。弊所では心配な点がある方へのサポートを強化していますので、まずはお気軽にご相談ください。
取得しやすい配偶者ビザですが
将来的に永住権を取得したいとお考えなら
2025年10月以降、在留資格審査が急激に厳格化しています。
配偶者ビザの取得時や更新時に曖昧な内容で申請してしまい、虚偽申請や在留資格不正取得などの違法性に関する疑念を一度でも持たれると、
永住権を取得するまで在留資格を維持していくのが困難になります。
長期間の日本在留を希望する方や、永住権の取得をお考えの方は、信頼できる「かかりつけ行政書士」を見つけて継続的なサポートを受けるようにしましょう。
在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」とは
配偶者ビザを申請できるのは、日本人か永住者の配偶者、日本人か永住者の実子または特別養子です。
普通養子や海外の類似制度による養子は該当しません。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、必ずしも日本人の扶養を受けなければならない訳では無く、その事が「家族滞在」の在留資格とは異なる部分であり、
日本人夫が専業主夫で外国人妻(申請人)が就労し、家庭の生計を立てている場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できますが、
夫婦ともに無職である場合は、婚姻生活の生計維持の、安定性・継続性に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。さらに、婚姻は、有効な婚姻である事が要件であり、内縁の妻や夫は含まれません。
さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、原則として、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。
「同居」と「家計同一」が大原則です。
許可の見通し
初回の申請の審査では、夫婦に収入や貯蓄などがあって、家族として生計がきちんと立てられる事(月の生活費20万円程度が目安)が重要なポイントとなり、
出会いから結婚までの説明に偽装結婚を匂わせるところがなければ概ね許可されますが、
最初に曖昧な内容で申請してしまうと、後々の更新申請や永住許可申請の際に矛盾を指摘されて、在留資格を失うことにもなりかねませんので注意しましょう。
3年または5年の在留許可を得たいのであれば、日本に馴染んで安定した生活を送っていて、素行にも問題がなく、公的義務もすべて果たしていることの証明が必要になります。
入管審査は「性悪説」に立って行われるため、疑念を持たれる可能性がある場合は、自らが先回りして正当性を立証しておかないと不許可になります。
特に、日本人に国際結婚の離婚歴があると審査は厳しくなり、離婚の経緯や再婚の真実性を示すための「理由書」とともに詳細な証拠資料の提出が必須となります。
離婚歴自体が直接不許可理由にはなりませんが、「日本にいさせるための結婚ではなかった」ことを具体的に説明・立証して疑念を払拭できないと許可を受けることが難しくなります。
偽装結婚でないことの証明は必須
不許可になるほとんどは、偽装結婚の疑惑が払拭できないケースです。
【 次のようなケースでは、かなりしっかりとした説明が必要になります 】
- ①夫婦の年齢差が5歳以上ある
- ②結婚相談所やマッチングアプリ等で出会った
- ③日本人配偶者の収入が少ない
- ④過去に短期間で結婚離婚を繰り返している
- ⑤交際期間が短い
- ⑥同じ家に住んでいない、または、ビザ取得後に住む家の準備が整っていない
- ⑦披露宴をしていない
- ⑧高齢での結婚
- ⑨交際が不倫から始まった
【 真実婚を立証するための重要ポイント 】
- ●どこが好きなのか、出会い、デート、プロポーズ、両親への挨拶、結婚式について、具体的なエピソード付きで詳しく説明する
- ●説明は写真やSNS履歴等の証拠と必ずセットにする(ない写真は撮り直すくらいの気持ちで)
- ●夫婦のコミュニケーションがしっかり取れていることをきちんと説明する
- ●複数のエピソードや証拠に齟齬や矛盾がないようにする
入管局には調査専門の部署があります。申請書類の内容と実態が一致していない場合はもちろん不許可となり、不許可の履歴は残り続けます。
過去の申請と一致しない内容で再挑戦することはできませんので、ありのまま正直に申請して判断を仰ぐことが最善策と言えます。
ページの先頭に戻る
3年か5年の許可を受けるためには
入管申請は書面での審査です。
申請者がどれほど信頼できる人物であったとしても、初回の申請では実態を見極めることが困難であるため、一旦は様子見として1年以下で許可されることが多いです。
3年以上の決定を受けるためには、出入国在留管理庁のホームページで案内されている資料を提出するだけでは足りません。
収入、住居環境、家族の関係性、子供の学校生活、日本での生活意欲などが、安定して継続していることを具体的に説明し、「家族構成や婚姻生活の継続性」を立証する資料を添付する必要があります。
もっとも、過去の申請内容との整合性が取れていて、信頼性が確保されていることが大前提であり、申請書類に矛盾や不信感がある場合は、長期間の許可が下りることはありません。
最近は在留資格審査においてもデジタル化が進み、過去の申請との矛盾点が一目瞭然となっていますので、
前回の申請時から変化があった場合や、過去にその場しのぎで誤った申請を行ってしまった方は、それらの説明や釈明も理由書に書き加えて、信頼の維持に努めることが重要です。
1年 以下の在留期間になってしまうケース
- ①前回の申請時に3年の在留期間を決定されていた人が、更新時に5年の要件①~④のいずれにも該当しなかった
- ②家族構成や婚姻生活の継続性を毎年確認する必要がある
- ③在留状況を毎年確認する必要がある
- ④日本での滞在予定期間が半年~1年以内
3年 の在留期間許可されるケース
- ①前回の申請時に5年の在留期間を決定されていた人が、更新時に5年の要件①~④のいずれにも該当しなかった
- ②5年の要件にも1年の要件にも該当しない
5年 の在留期間が許可されるケース
次のすべてに該当すること
- ①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出や変更、所属先の変更の届出等)を履行している
- ②各種の公的義務を履行している
- ③学齢期(義務教育期間中)の子供を学校に通わせている
- ④所得税及び住民税を納付している
- ⑤結婚後の同居生活が3年以上あって、今後も配偶者の身分に基づく婚姻生活の継続が見込まれる
ページの先頭に戻る
国際結婚手続きの流れ
国際結婚の手続きや必要書類 は国によって異なります。ここではフィリピンの例をご紹介します。
- ①出入国在留管理庁でフィリピン人婚約者の短期滞在ビザ90日枠を取得します(日本人婚約者が招へい人&身元保証人を担う、招へい目的は「日本で結婚手続きを行いたいから」と記載)
- ②フィリピン人婚約者が現地で書類収集(出生証明書、独身証明書(使用目的には「Marriage」と記載)、すべての書類にフィリピン外務省の認証(DFA authenticated)アポスティーユ(Apostille)が必要) 最低でも日本の役所用とフィリピン領事館用の2部必要(予備もあったほうがよい)
- ③フィリピン人婚約者が日本に渡航
- ④日本にあるフィリピン大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を受領
- ⑤市役所・区役所へ婚姻届を提出
- ⑥フィリピン大使館・領事館に婚姻を報告 結婚証明書を受領(ビザ申請に必要)
- ⑦出入国在留管理庁で配偶者ビザ取得(配偶者ビザ取得手続きの流れは下記参照)
- ⑧フィリピン人婚約者は一旦帰国(帰国せずに特例措置で短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できる場合もあり)
ページの先頭に戻る
配偶者ビザ取得までの流れ
海外在住の配偶者 を日本に呼び寄せる場合の入国までの流れ
- ①両国での正式な婚姻手続き(上記参照)
- ②「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請書を作成(申請書+添付資料)
- ③出入国在留管理庁への申請
- ④審査
↓(許可)
- ⑤「在留資格認定証明書」の交付を受けて、海外在住の家族に送付
- ⑥海外在住の家族が現地の日本領事館に「在留資格認定証明書」を提示して「ビザ(上陸許可)」の発給を受ける
- ⑦「在留資格認定証明書」の交付から90日以内に日本に入国し、空港で在留カードを受け取る
在留中の配偶者 の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合の手続きの流れ
- ①両国での正式な婚姻手続き
- ②「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請書を作成(申請書+添付資料)
- ③出入国在留管理庁へ申請
- ④審査
↓(許可)
- ⑤出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取る
ページの先頭に戻る
就労ビザから変更する場合の注意点
就労系のビザから変更する場合は、「就労制限がなくなること」が最大のメリット だと思います。
就労系のビザを持っていて、これから転職を考えている場合、再就職の見込みがない場合、就労ビザでは就労できない職種で働きたい場合は、かなりメリットが大きいです。
配偶者ビザを取得すれば、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でもできますし、何時間でも働けますが、
日本人と離婚すれば日本に住めなくなってしまうことだけは忘れないでください。
デメリットは、多くの場合在留期間が1年になってしまうこと でしょう。
永住許可の取得を考えている方であれば、配偶者ビザを取得することで永住許可申請時に優遇措置を受けられますので有利になりますが、
永住許可の取得を考えていない方の場合は、毎年のビザ更新が面倒になったり、「家族滞在」で呼び寄せている子の在留資格を「定住者(日本人の配偶者の方が扶養する場合)」に変更する必要があるなどのデメリットもあるので注意が必要です。
就労系のビザから変更する場合は、所属機関での届出(外国人雇用状況の届出等)にも影響しますので、会社に事前に相談しておくようにしてください。
(参考)就労系ビザの詳細
ページの先頭に戻る
離婚や死別後も日本に住めるケース
離婚や死別によって「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」に該当しなくなると在留資格を失うことになりますが、
次の理由で「定住者」に変更できれば日本に住み続けることができます。
ただし、配偶者である日本人や永住者と離婚してから14日以内に届出を行わなかった、または、6ヶ月以内に他の在留資格に変更しなかった場合は、
20万円以下の罰金(19条の16第3号)に処せられるほか、在留資格の取消し対象にもなり、在留状況不良の扱いを受けて他の在留資格への変更すら認められなくなる危険性が生じますので注意してください。
「定住者」は、特別な理由がある場合に限り居住を認める在留資格で、
「在留資格認定証明書」により外国から呼び寄せることが可能な「告示定住」と、他の在留資格からの在留資格変更のみによる「告示外定住」があります。
「離婚定住」「死別定住」「日本人実子扶養定住」は告示外定住にあたり、許可のハードルは「告示定住」よりも高くなります。
- ※告示外定住の審査期間は6か月~8か月程度になっています。
在留期限の前日までに変更申請をすれば2か月間は在留を認められますが、それ以降は入管の指示に従うことになります。
在留期限が迫っている場合は速やかに変更申請をしましょう。
1.日本人または永住者の配偶者として在留していた外国人が離婚や死別をし、引き続き在留を希望する場合
- ①日本においておおむね3年以上の婚姻生活が継続していること
- ②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- ③日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
- ④法令遵守と納税など公的義務を履行していること(離婚後14日以内に届出している、風俗関係の仕事をしていない等も含む)
- ※以上の条件に加え、婚姻の実態や離婚するに至った経緯など、様々な事情から総合的に判断されることになります。
2.日本人の実子を監護・養育している場合
「日本人の実子」は、日本国籍を有する実子の他にも、日本国籍を有しない実子(「日本人の配偶者等ビザ」で在留する子ども)が含まれ、以下の条件を満たしている場合にビザが認められ得ます。
- ①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- ②日本人との間に出生した子を監護・養育しており、日本人の実子の親権者である、または、現に相当期間その実子を監護・養育していること
- ※この趣旨は、日本人の実子が安定した生活を営めるようにすることと、幼い子供とその親との関係への人道上の配慮であり、ビザの付与もこのような観点から総合的に判断されることになります。
ページの先頭に戻る
「連れ子」の在留資格は?
外国人配偶者の「連れ子」の在留資格について
日本人と外国人が国際結婚し、外国人の連れ子を日本に連れてきたい場合の在留資格は多くの場合「定住者」になります。
「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、
連れ子ビザ(定住者告示6号ニ)は、「ハーグ条約に抵触せず」「申請要件を満たしていることを提出書類で立証できれば」概ね許可されます。
連れ子の親である外国人の在留資格が「永住者」であれば、連れ子の在留資格は「永住者」または「永住者の配偶者等」になり、
外国人配偶者が就労ビザを持っていれば、連れ子は「家族滞在」で日本に在留できる可能性もあります。
「定住者」は「永住」と同様で就労制限はありませんが在留期間の定めがあり、期間の満了時にはビザの変更または更新か帰国を選ばなければなりません。
「定住者」として継続して5年以上在留していて、素行が善良であり、独立して生計を営むに足りる収入(300万円程度)があれば、永住許可の申請も可能です。
外国人配偶者に連れ子がいる場合は、配偶者ビザの申請時に同時申請することもできますし、配偶者ビザ取得後に申請して呼び寄せることも可能です。
連れ子ビザ(定住者告示6号ニ)の申請要件
「すべての準備ができている状態」で、「入管法の現在の運用に即した内容で作成した理由書」を添付して申請する必要があります。
面接を求められることも多く、説明が不十分で一度不許可になると、リカバリーがたいへん難しくなる在留資格です。
- ①親の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であること
- ②実子であり親権があること
ハーグ条約(子の奪取の民事上の側面に関する条約)の国内実施のため、親権又は監護養育権が外国人配偶者にあることを証明する必要があります。
多くの国は裁判離婚を採用していることから、子供のに親権又は監護養育権の記載がある、離婚時の裁判所の判決文書を提出するのが一般的です。
もし、親権又は監護養育権が別れた配偶者との記載であれば、改めて裁判をして判決文書を取得しねければなりません。
なお、前の配偶者と死別していたり、未婚で出産しているのであればその事を証明する書類を提出することになります。
- ③未成年かつ未婚であること
許可をうけるときに未成年でなければなりません。実質的に、申請できるのは15歳くらいまでです。
- ④日本人または日本人の配偶者(親)の扶養を受けること
子のが日本での活動は親の扶養を受けることが要件ですので、就労させることはできません。
義務養育を受けることはもちろん、15歳以上の者でも、日本語学校や高校での就学させなければなりません。
その事を疎明するため、教育委員会や就学予定の学校とのやり取りを文章で説明することになります。
就業させることはなく、日本人配偶者が十分な日本の教育を受けさせて、日本の文化や社会に適応できる人材に育てる意思があることの証明を求められます。
連れ子ビザ(定住者告示6号ニ)の申請に必要な書類
- ①申請書
- ②写真(3cm x 4cm)
- ③日本人の戸籍謄本
- ④日本人の住民票(世帯全員)
- ⑤扶養者の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
- ⑥扶養者の在職証明書(自営業者は確定申告書の控え、営業許可証など)
- ⑦身元保証書
- ⑧血縁関係を証明する資料(本国で発行された出生証明書+出生医学証明書 日本語訳を添付)
- ⑨理由書(扶養を受けなければならない理由を説明したもの 入管法の運用に沿った内容で)
ヒアリングさせていただく内容
まずは ご夫婦の現在 について教えていただきます
- ①お二人のお名前、年齢(年齢差)、国籍、現在の在留資格
- ②住んでいる(住む予定の)場所(持ち家、賃貸、家賃)
- ③お互いの母国語をどの程度理解できますか
- ④普段の会話で使っているのは何語ですか
- ⑤初婚ですか再婚ですか
- ⑥お子さん(日本人側の実子か養子、外国人側の連れ子、その他同居の扶養家族)はいますか
- ⑦お二人の職業、契約形態、職務内容、勤続年数、世帯年収(所得金額)
- ⑧過去5年間の交通違反の有無やその他で警察にお世話になったことがなかったか
- ⑨住民税・年金・健康保険の未納や滞納の有無
- ⑩オーバーステイや強制退去の履歴の有無(あった場合はその理由)
交際と結婚 を立証できる具体的な資料を持っているか確認します
- ①正式に結婚したのはいつですか 日本の戸籍に記載されていますか 本国の領事館で結婚証明書を取得していますか
- ②どこで知り合いましたか
- ③交際経緯に関して立証できる具体的な資料はありますか(写真・手紙・SNS履歴、航空チケットなど)
- ④互いの両親に挨拶に行ったことを立証できる具体的な資料はありますか(写真・手紙・SNS履歴、航空チケットなど)
- ⑤結婚式を行ったことを立証できる具体的な資料はありますか(結婚式の写真 友人や同僚から祝福されている写真 お祝いの手紙 その他具体的なエピソードなど)
- ※離婚歴については、互いに知らないケースがたまにあります。フィリピンでは裁判を経ないと正式な離婚が成立しないことにも注意が必要です。審査の段階になって隠し事が発覚すると許可が得られなくなってしまいますので、申請する前に互いに確認しておいてください。
配偶者ビザの 更新 をご依頼の方には次のお話しもお聞きします
- ①夫婦仲はどのような状態ですか 別居していませんか(別居している場合はその理由(単身赴任なども含む))
- ②住居地が変わっている場合、届出をしていますか
- ※離婚や死別によって「日本人の配偶者等」に該当しなくなったとしても、他の在留資格に変更できれば日本に住み続けることができます。
実質的に離婚しているのに夫婦関係を装ったり、別居しているのに同居を装ったりすると、在留資格を失うだけでなく、日本に住む権利を失うことになってしまいますので、
DVなどの正当な理由で在留資格の維持が困難な状態に陥っている場合は、事前に自治体や出入国在留管理庁の相談窓口を利用しておくようにしてください。
ページの先頭に戻る
ご用意いただく資料のご案内
不許可リスクを低減できるよう、申請書と理由書は、ヒアリングしながら弊所で作成を代行 します。
弊所では、お客様が収集できる資料は出来る限りお客様にご用意していただくことで、他事務所の半額程度の料金でサービスを提供できるよう配慮しています。
下にある添付資料につきましては、お客様にご用意いただくことを原則としますが、収集方法がわからないものは支援させていただきますのでご安心ください。
申請人が日本人の配偶者であって、新規に在留資格を取得する場合
- ①申請人の写真(縦472px 横354px、3ヶ月以内に撮影したもの)
提出写真の規格はこちら 写真画像の編集は弊所で行います
- ②パスポートのコピー
- ③申請人の本国から発行された結婚証明書
- ④日本人配偶者の戸籍謄本
- ⑤日本での滞在費用を証明する資料
- ●申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の納税証明書(未納税がないもの)および住民税の課税証明書
- ●住民税の証明ができない場合は、預貯金通帳のコピー、雇用予定証明書、採用内定通知書等でもよい
- ⑥日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3ヶ月以内でマイナンバーが不記載のもの)
- ⑦質問書
- ⑧質問書の内容を証明するための写真やSNS履歴等
- ⑨身元保証書
申請人が日本人の配偶者であって、在留資格を更新する場合
- ①申請人の写真(縦472px 横354px、3ヶ月以内に撮影したもの)
提出写真の規格はこちら 写真画像の編集は弊所で行います
- ②申請人の本国から発行された結婚証明書
- ③パスポートのコピー
- ④在留カードのコピー
- ⑤日本人配偶者の戸籍謄本
- ⑥日本での滞在費用を証明する資料
- ●申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の納税証明書(未納税がないもの)および住民税の課税証明書
- ●住民税の証明ができない場合は、預貯金通帳のコピー、雇用予定証明書、採用内定通知書等でもよい
- ⑦日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3ヶ月以内でマイナンバーが不記載のもの)
- ⑧身元保証書
申請人が日本人の子として出生した実子・特別養子である場合
- ①申請人の写真(縦472px 横354px、3ヶ月以内に撮影したもの)
提出写真の規格はこちら 写真画像の編集は弊所で行います
- ②パスポートのコピー
- ③日本人親の戸籍謄本
- ④日本で出生した場合は、次のいずれかの文書
- ●出生届受理証明書
- ●認知届受理証明書
- ⑤海外で出生した場合は、次のいずれかの文書
- ●出生国の機関から発行された出生証明書
- ●出生国の機関から発行された認知に係る証明書
- ⑥特別養子の場合は、次のいずれかの文書
- ●特別養子縁組届出受理証明書
- ●日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本および確定証明書
- ⑦日本での滞在費用を証明する資料
- ●申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の納税証明書(未納税がないもの)および住民税の課税証明書
- ●住民税の証明ができない場合は、預貯金通帳のコピー、雇用予定証明書、採用内定通知書等でもよい
- ⑧日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票(発行日から3ヶ月以内でマイナンバーが不記載のもの)
- ⑨身元保証書
【定住者】日本人の配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子の場合(外国人の連れ子)
- ①申請人の写真(縦472px 横354px、3ヶ月以内に撮影したもの)
提出写真の規格はこちら 写真画像の編集は弊所で行います
- ②パスポートのコピー
- ③実親の配偶者である日本人の戸籍謄本
- ④実親の配偶者である日本人の世帯全員の記載のある住民票
- ⑤実親の配偶者である日本人の住民税の課税証明書および納税証明書
- ⑥実親の配偶者である日本人の職業・収入に関する資料
- ●会社員である場合は、在職証明書
- ●自営業である場合は、確定申告書の控えのコピー(営業許可が必要な業種の場合は営業許可証も)
- ●無職である場合は、預貯金通帳のコピー等
- ⑦身元保証書
ページの先頭に戻る
HOME 永住許可 配偶者ビザ 就労ビザ 料金案内
Copyright 1995-2026 シモン行政書士事務所
〒206-0822 東京都稲城市坂浜3-30-14
042-401-3247
gs3.sakamoto@information-strategy.jp
はじめてのご連絡は上のフォームからお願いします